「被扶養者が不動産を売却したら扶養から外れるってホント?」
「被扶養者が不動産を売る際に注意すべき点は?」
こんな疑問にお答えします。
主婦や扶養の範囲内で働いている被扶養者が不動産を売却して、給与以外の所得が48万円を越えた場合、「配偶者控除」が受けられなくなる可能性があります。
「配偶者控除」が受けられなくなると、配偶者の税金が高くなったり、社会保険を利用できなくなったりするため、被扶養者が不動産を売却する場合はさまざまな注意が必要です。
そこで今回は、被扶養者が不動産を売却するときの注意点や、不動産売却した結果「配偶者控除が受けられなくなる」、「社会保険の扶養から外れてしまう」条件などを解説していきます。
\厳選2,100社と提携・国内最大級!/
目次
不動産売却で年に48万円を越える所得があると配偶者控除が受けられなくなる
不動産売却後、配偶者控除が受けられなくなる基準は、「年間の所得が48万円を越えた」場合です。
配偶者控除の利用条件は年間所得が48万円以下であること
いわゆる扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。簡単にいうと、前者の扶養は「被扶養者を養っている人の税金が安くなる」という制度のことです。
たとえば、サラリーマンと専業主婦の家庭では、専業主婦には収入がありません。
この場合、サラリーマンは自分の収入で妻を「扶養」しているため、給与所得控除や基礎控除に加えて、「配偶者控除」という控除を利用することができます。
サラリーマンの場合、毎年収める所得税や住民税額は、「給与ー各種控除の合計額」に税率をかけて求めるため、控除が増えると税金が安くなるという仕組みです。
ただ、配偶者控除は、だれでも無条件に利用できるものではありません。税務上のルールでは、
- 婚姻届を提出した夫婦
- 一方の収入で生活している(生計を一にしている)
- 扶養される側の年間所得が48万円以下
- 青色・白色申告者の専従者として給料をもらっていない
上記の場合にのみ配偶者控除を利用できる、つまり扶養に入れると決められています。
「扶養に入っている」ということは、「相手に養われている」ということなので、一定以上の収入があると自動的に扶養から外れてしまうのです。
結婚していること、一方の収入で生活していることは、非常にわかりやすい基準といってよいでしょう。
最後の青色・白色申告に関する部分は、法人化していない個人経営の事務所やビジネスをしている場合にのみ関係のある条件なので、サラリーマン世帯なら気にする必要はありません。
ポイントは、所得の考え方です。所得とは、「所得=収入ー経費ー控除」という計算で求める数字のことで、税の世界では収入ではなく所得を使って税額を求める決まりになっています。
不動産売却時の譲渡所得は以下の式で求められます。
譲渡所得=不動産売却価格ー取得費ー譲渡費用
たとえ不動産が1,000万円で売れても、取得費・譲渡費用を差し引いて所得が48万円以下になれば、配偶者控除は受けることができます。
なぜ48万円が1つの基準になっているのかというと、国民全員がもらえる「基礎控除」が、年間48万円(令和1年度までは38万円)だからです。
基礎控除は、正社員・派遣社員・アルバイト・自営業者のだれでも平等に使える控除のことで、年間の収入・所得が基礎控除を下回る場合、税のルール上は「年間の所得なし」という扱いです。
社会保険は収入が年130万円未満なら扶養から外れない
配偶者控除に関しては、「年間所得48万円」が受けられなくなるボーダーラインでした。
しかし、社会保険に関しては、「年収130万円未満」なら、収入や所得があっても扶養から外れません。
理由は簡単で、健康保険や厚生年金といった社会保険は、独自の加入資格を設定しているからです。
そのため、「配偶者控除は使えないが、社会保険の扶養に入っている」という状態になる場合もあります。
\厳選2,100社と提携・国内最大級!/
扶養から外れると税金が高くなる!被扶養者が不動産売却をする場合のリスクと注意点

被扶養者が不動産売却をする場合、「配偶者控除を受けられるか」「社会保険上の扶養から外れるかどうか」を考えながら売却プランを立てることが重要です。
以下のリスクや注意点を知っておきましょう。
- 扶養から外れることによる納税負担の増加
- 増税による手取りの減少
配偶者控除を受けられなくなると税金が高くなる
不動産売却をした結果、年間の所得が48万円を越えてしまうと、配偶者控除が受けられなくなり、税金が高くなってしまいます。
不動産を売った本人には、資産を売却して得た所得にかかる「譲渡所得税」が、「配偶者控除」を失う配偶者には、所得が増えたことによる所得税・住民税の増額が降りかかってくるため注意が必要です。
増税の負担によっては、不動産を売って手に入れた利益が消え飛んでしまうため、被扶養者が不動産売却をする場合は、「本当に売った方がいいのか」も考えましょう。
会社から扶養手当をもらっている場合1年間手取りが下がる
家族が扶養から外れた場合、会社からもらっている「扶養手当」がなくなる可能性があります。手当がなくなれば当然手取りや額面年収も下がってしまうため、収入ダウンは避けられません。
また、社会保険の扶養条件である「年収130万円」以上の収入を不動産売却で得た場合は、扶養から外れたあとに別途健康保険へ加入する必要があります。
夫または妻の会社で入っている社会保険の脱退や、新たな保険の加入など、手続きが増える点にも注意が必要です。
年間所得の計算にはパート・アルバイトなどの収入も含まれる
パートやアルバイトなどで給与所得がある場合、不動産売却等の給与以外の所得が48万円以下かどうかで扶養から外れるかどうかが決まります。
たとえば、「扶養の範囲内ぎりぎりの収入になるようシフトを調整している」「税金がかからないように働いている」という人は、不動産を売却した年だけ扶養から外れてしまうので、注意が必要です。
参考:【被扶養者必見!】不動産売却で健康保険料が上がるってホント?
3,000万円の特別控除を利用しても配偶者控除は受けられなくなる
「マイホーム」や「相続した不動産」を売却する場合、不動産の売却代金から最大3,000万円控除することができます。
不動産売却の特別控除を利用すれば、ほとんどのケースで譲渡所得税がかかることはありません。
しかし、「配偶者控除を受けられるかどうか」は、「3,000万円の特別控除を適用する前」の所得によって判断されます。
3,000万円の特別控除で譲渡所得税をゼロにできても、配偶者控除が適用されなくなる場合があるため、家を売る場合はあらかじめ翌年の納税負担が増えることも家族で話し合っておきましょう。
不動産を売却したら翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしよう

不動産を売却した場合、利益が出たかどうかに関わらず、基本的には確定申告手続きをしましょう。
日本では、個人が手に入れた所得や控除を自分で計算し、税務署に申告するという原則を採用しています。税法上、無申告の人に対するペナルティーは重いです。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日前後の期間に提出する必要があるので、譲渡所得税がかかる場合は忘れずに申告手続きを終わらせましょう。
所得が48万円を越えても「配偶者特別控除」を利用できるケースがある
なお、所得が年間48万円を越えても、133万円以下なら「配偶者特別控除」を利用可能です。
配偶者控除に比べると控除できる金額は下がりますが、多少でも税金が安くなるため、できれば年間の所得が133万円以下になるように、取得費や譲渡費をもれなく反映しましょう。
\厳選2,100社と提携・国内最大級!/
不動産の購入費など!譲渡所得を抑えるために知っておきたい取得費の内訳
先ほどもご紹介しましたが、譲渡所得は、以下の式で求められます。
譲渡所得=不動産売却価格ー取得費ー譲渡費用
簡単にいうと、取得費と譲渡費用が高ければ、売却価格が高くても年間の所得を48万円以下に抑えられます。
ここからは取得費と譲渡費用の内訳を見ていきましょう。
売却する土地・建物の購入費用
取得費のなかで、もっとも金額的に大きいのが土地・建物の購入費用です。
たとえば、20年前に2,000万円で購入した建売住宅を1,500万円で売却した場合、ざっくり計算して購入費の半額程度を売却価格から差し引くことができます。
購入費用を丸ごと引けないのは、建物の経年劣化を割り引く必要があるからです。
売却予定の不動産を購入する際に支払った仲介手数料
不動産を購入する際、物件や土地探しを不動産会社に頼った場合、仲介手数料という報酬を支払う必要があります。
譲渡所得の計算では、不動産購入時に払った仲介手数料も取得費としてカウント可能です。
仲介手数料の上限額は、「不動産価格×3%+6万円」なので、数千万円の物件を購入していれば、仲介手数料だけで数十万円所得を減らすことができます。
登録免許税・不動産取得税・印紙税などの税金
そのほか、不動産購入時にかかった税金も、取得費です。納税費用がわかる書類を残していれば、納めた税金も取得費として処理しましょう。
仲介手数料や測量費など!譲渡所得を低く抑える譲渡費用の中身とは

譲渡所得を抑えるために必要なもう1つの経費が、仲介手数料や測量費などを含む、譲渡費用です。
取得費が「不動産購入時」にかかった費用であることに対して、譲渡費用は「不動産売却時」にかかったお金が対象です。
不動産売却時に支払う仲介手数料
不動産売却時に業者へ仲介手数料を支払っている場合、取得費に仲介手数料を入れていても、別途譲渡費用にすることが可能です。
参考:不動産売却で仲介手数料っていくらかかるの?失敗しないための基礎知識
売却に向けて負担した土地・建物の測量費
一般的には、不動産を売却するにあたって、売主が測量費(現況測量または確定測量)を負担します。測量費は不動産を売却するためにかかった費用なので、譲渡費用(経費)として扱いましょう。
参考:土地売却における「測量」の必要性や流れ・費用について徹底解説
不動産会社に実費の広告を頼んだ場合の広告費
通常、不動産会社に支払う仲介手数料には、広告費用も含まれています。
しかし、売主からの依頼で特別な広告を頼んだ場合は、別途実費で広告費の支払いが必要な場合があります。このときに負担した広告費は、譲渡費用(経費)に組み込むことができます。
参考:不動産売却の広告費は会社が負担!その内容や売れる広告の特徴を解説
他人に貸していた物件を売る場合は住民への立ち退き料も含められる
もし、賃貸住宅を売却する際に、現在の住民へ立ち退き料を払って引っ越してもらった場合は、立ち退き料も譲渡費用(経費)として処理可能です。
その他、不動産売却にかかる費用は下記で詳しく解説しています。
不動産売却で損をしないように優良な不動産会社を選ぼう:まとめ
不動産を売って年間48万円以上の譲渡所得がある場合、配偶者控除を受けられない可能性があります。
この場合、翌年の所得税や住民税が高くなるため注意が必要です。
不動産を売るときは、「不動産売却によって入ってくるお金」と「不動産売却によって出ていくお金」を比較して、トータルで損をしないように売却プランを立てましょう。
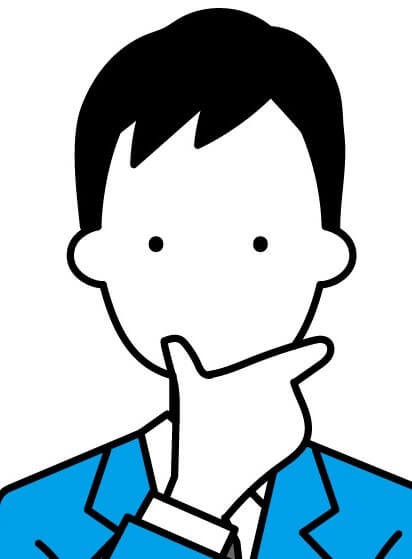
信頼できる不動産会社選びです!
























このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)