「不動産を売却するとき瑕疵担保責任は必要なの?」
「そもそも瑕疵担保責任ってなに?」
こんな疑問にお答えします。
瑕疵担保責任とは、「不動産売却後に買主の知らない住宅の問題点が発覚した場合、売主が損害賠償や売買契約の解除など責任を負う」という不動産売却取引上のルールのことです。
瑕疵担保責任は、民法上のルールなので、買主から住宅の瑕疵に関する請求をされた場合、原則拒否することができません。
ただし、売買契約書の内容次第では、瑕疵担保責任の保証期間を変えたり、瑕疵担保責任そのものを免責したりすることもできるため、余計なトラブルを防ぐためにも瑕疵担保責任の基本を押さえておきましょう。
また、2020年4月の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」という名前に変わりました。
法改正に伴い、売主はさらに幅広い範囲で売却する物件に責任を負う必要がでてくるため、契約不適合責任に関する知識も必要です。
そこで今回は、瑕疵担保責任の内容や具体例、民法改正による影響などついて解説していきます。
\厳選2,100社と提携・国内最大級!/
目次
瑕疵担保責任とは不動産売却時に売主が負う責任のこと

瑕疵担保責任とは、不動産売却後に隠れた瑕疵が見つかった場合、売主が負うべき損害賠償請求や売買契約の解除といった責任のことです。
瑕疵の内容によっては、数百万円単位の出費が必要です。
瑕疵担保責任について適当に処理していると、取引後何年も経過してから「隠れた瑕疵が見つかったので、売買契約を白紙に戻してほしい」と要求される可能性もあるので注意が必要です。
とはいえ、多くの人にとって、「瑕疵担保責任」という用語すら初めて耳にする言葉でしょう。
不動産の用語や法律用語は内容や説明が難しいため、まずは瑕疵担保責任の概要を解説します。
- 売却した不動産に瑕疵がある場合は売主が責任を取る必要がある
- 瑕疵を黙ったまま売ると買主から売買契約の解除や損害賠償請求をされる
- 民法では「買主が隠れた瑕疵に気づいてから1年」が保証期限
- 物件によっては瑕疵担保責任を免責して売却することもできる
- 瑕疵担保責任保険に加入すれば隠れた瑕疵が見つかった場合保険金が下りる
- 不動産売却前に瑕疵をすべて伝えておけば損害賠償請求される心配はない
順に解説していきます。
売却した不動産に瑕疵がある場合は売主が責任を取る必要がある
瑕疵担保責任は、不動産の売却後、買主の知らない住宅の欠陥や問題点が見つかった場合、売主が損害賠償をしたり、契約を白紙に戻して代金を返還したりする義務のことです。
不動産売却では、日用品や食料品の買い物と違って、非常に大きな額のお金をやり取りします。しかし、不動産の劣化や欠陥は、住宅を外から見てすぐにわかるものばかりではありません。
高い買い物であるにも関わらず、売ったあとは一切補償しないという取引を認めると、買主側のリスクが高くなってしまいます。
不動産購入のリスクが高まれば、当然中古の不動産は売れません。
そこで、買主がより気軽に不動産を購入できるように、「何かあった場合は売主が責任を取る」という瑕疵担保責任が設定されているのです。
瑕疵を黙ったまま売ると買主から売買契約の解除や損害賠償請求を求められる
瑕疵担保責任では、「隠れた瑕疵」を対象にしています。
隠れた瑕疵とは、「買主が気づいていない住宅の欠陥や問題点」のことです。
たとえば売却予定の物件が過去シロアリ被害にあっており、その事実を黙って不動産売却した場合、買主から損害賠償請求など求められると売主は責任を持って損害賠償請求等を受ける必要があります。
小さな瑕疵ならともかく、住宅の基礎や水回りに瑕疵が見つかると、数百万円単位の請求をされる可能性があります。
損害賠償で対応できない場合、売買契約そのものの撤回を求められるため、不動産売却時に受け取った金額の返金も必要です。
不動産売却を終えた直後ならともかく、数ヶ月以上経過してから多額の損害賠償を負担することになれば、請求されても払えない人が大半でしょう。
将来の予期せぬ出費を避けるために、売主は瑕疵担保責任の詳細を理解しておく必要があるのです。
民法では「買主が隠れた瑕疵に気づいてから1年」が保証期限
不動産売却における瑕疵担保責任の保証期限は、原則として、「買主が隠れた瑕疵に気づいてから1年以内」となります。
ただし、瑕疵担保責任は、売買契約の内容次第で保証の範囲や期限を変更することが可能です。
多くの場合、実際の不動産売却現場では、「買主が隠れた瑕疵に気づいてから2~3ヶ月」程度瑕疵担保責任の期間として採用されています。
物件によっては瑕疵担保責任を免責して売ることもできる
売主と買主がお互い納得していれば、瑕疵担保責任を免責することも可能です。
もし、瑕疵担保責任を絶対に解除できない法的な義務にしてしまうと、築年数の古い住宅など、隠れた瑕疵のある可能性の高い物件を売却する際の売主負担が大きくなりすぎてしまいます。
遠方にある古い実家を相続した場合など、費用をかけて物件の瑕疵を明らかにする余裕がない場合は、事前に不動産会社に相談し、瑕疵担保責任そのものを免責する内容を売買契約に盛り込みましょう。
なお、不動産の売主が不動産業者である場合、瑕疵担保責任を免責することはできません。
不動産売却のプロである業者側が、買主を言いくるめて問題のある物件を売却するといったトラブルを予防するためです。
瑕疵担保責任保険に加入すれば隠れた瑕疵が見つかった場合保険金が下りる
瑕疵担保責任保険という保険に加入しておけば、もし売却後に買主が隠れた瑕疵を見つけ、賠償を求められた場合に保険を利用できます。
保険料の支払いや保険会社による住宅のチェックは必要になりますが、最大で1,000万円程度まで補償してもらえるので、瑕疵担保責任を設定する場合は、保険の利用を検討しましょう。
不動産売却前に瑕疵をすべて伝えておけば損害賠償請求される心配はない
瑕疵担保責任の対象は、「不動産売却時に買主が気づかなかった瑕疵が明らかになったとき」です。
そのため、不動産売却の際にあらかじめすべての瑕疵を説明しておけば、損害賠償等を請求される心配はありません。
雨漏りや法的な不備・事故物件など!瑕疵担保責任の「瑕疵」について解説

瑕疵担保責任の瑕疵は、主に以下の種類に大別されます。
- 物理的な瑕疵
- 法的な瑕疵
- 精神的な瑕疵
物理的な瑕疵:雨漏りやシロアリによる被害など
- 雨漏り
- 基礎の劣化・破損
- シロアリ被害
物理的瑕疵が見つかった場合、瑕疵の程度に応じて損害賠償請求をされることになります。
法的な瑕疵:建築基準法違反の事実など
- 現状で建築基準法に違反している
- 市街化調整区域や再建築不可などで土地の用途や建て替えが制限されている
- 土地が道路に接していない(接道していない)ため別途工事が必要
目で見てわかる欠陥ではないものの、不動産売却後に買主が家を建てたり、建て替えたりする際に問題が発覚することが多く、トラブルになりやすいです。
精神的な瑕疵:事故物件や墓地が近くにある物件など
- 殺人事件等の現場になった
- 異臭・騒音などの問題がある
- 近隣に墓地や反社会的勢力の事務所がある
安心して暮らすのが難しい問題は、精神的な瑕疵として扱われます。
瑕疵担保責任には時効がないため、どれだけ昔に精神的瑕疵があったとしても、瑕疵の内容を知っている場合は買主へ伝える必要があります。
告知義務のトラブルに関する詳しい記事は下記をご覧ください。
>>事例で学ぶ!不動産売却のトラブル【事故物件の告知義務編】
2020年の民法改正で瑕疵担保責任が廃止!?法改正による影響を解説
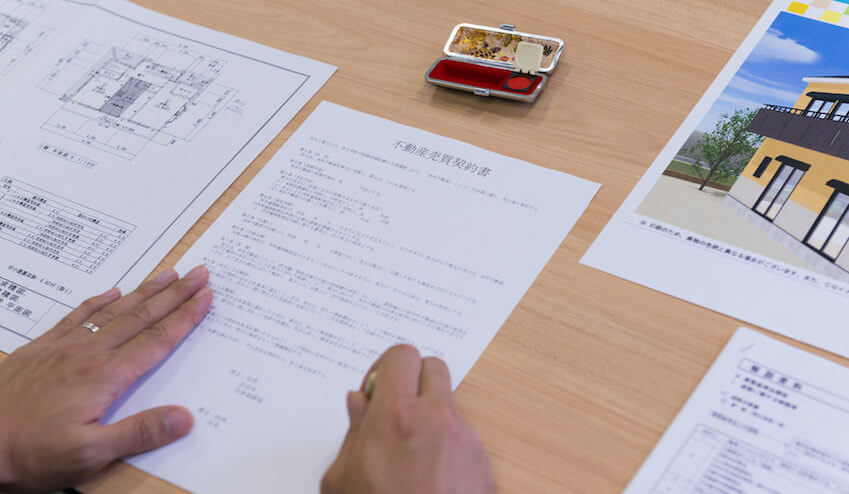
2020年の4月に民法の大規模改正が行われました。それまでに交わした不動産売買契約は以前のまま瑕疵担保責任が適用されます。
新しい民法では瑕疵担保責任が廃止され、「契約不適合責任」という責任が新しく作られました。
売主が負う責任の範囲も、トラブルを避けるために必要な売買契約書の作り込みも大きく変わってくるため、法改正による影響も押さえていきましょう。
2020年の民法改正で瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わった
契約不適合責任とは、「事前の説明と少しでも違うものを渡した場合、売主が責任を取る」という新たな売主の責任です。
瑕疵担保責任では、売主が瑕疵を知っていたかどうかが非常に大きな問題になります。
裁判になったとき、売主が瑕疵を知らなかったと証明できれば、隠れた瑕疵があっても責任を追わなくてもよいからです。
ただ、知っていることを証明する場合はともかく、知らなかったことを証明するのは、売主にとっても買主にとっても簡単なことではありません。
そのため、改正後の民法では、瑕疵があったかどうかやその事実を知っていたかどうかではなく、「契約書で説明した通りの不動産を引き渡せたかどうか」で売主の責任を判断するようにしたのです。
「こういった瑕疵がある」「瑕疵について確認していない物件を売る」など、瑕疵が存在することも存在しないことも細かく売買契約書に書き込む必要があるため、売主が責任を負う範囲は瑕疵担保責任よりも広くなります。
民法改正後は契約書の入念なチェックが必要不可欠
民法改正後の契約不適合責任では、「契約書で定めた内容の通り不動産売買をしているか」がもっとも重要なポイントです。
- 物件の引き渡し日
- 引き渡しの方法
- 不動産の現状
- 付帯設備表(住宅の設備に関してまとめた書類)
- 告知書(設備以外の問題点についてまとめた書類)
これまでおおまかな記入でも何とかなっていた部分まで、細かく文書化しておく必要があります。
書類の文量が増えるとチェックも大変になりますが、「契約書に記載されていない事項」があると問答無用で契約不適合責任を追求されてしまうため、法改正後は必ず自分でも売買契約書を確認しましょう。
参考:不動産売却で重要な「付帯設備表」宅建士が6つのポイントで解説!
瑕疵担保責任保険や契約不適合責任の免責も効果的
なお、瑕疵担保責任と同様に、保険や契約不適合責任そのものの免責も可能です。
法改正の直後は、売主・買主・不動産業者の全員が新しい手続きに戸惑う可能性が高いため、法改正後に不動産売却をする場合は、トラブルへ発展しないように準備を整えましょう。
瑕疵担保責任に関するトラブル事例は下記をご覧ください。
>>事例を知って事前に回避!不動産売却時のトラブル【瑕疵担保編】
不動産を売却するときは瑕疵担保責任や契約不適合責任に注意:まとめ
不動産売却をするときは、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負う必要があります。
瑕疵担保責任は法律で決められた売主の責任なので、損害賠償請求や売買契約の撤回を求められた場合、「そんなものは知らない」と拒否することはできません。
また、2020年4月1日に民法の大改正によって瑕疵担保責任が廃止され、従来の瑕疵担保責任よりも広範囲に責任を負う、契約不適合責任が作られました。
不動産の専門知識がないと、制度の変更に対応することができません。不動産トラブルを予防するためには、優良な不動産会社の協力が必要です。
不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
























このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)