「不動産売却時の瑕疵担保責任(契約不適合責任)ってなに?」
「そもそも不動産売却時に瑕疵担保責任は必要?」
こんな疑問にお答えします。
不動産を売却するとき、売主が気をつけてなければならない事項として「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」というものがあります。
仮に、売主が瑕疵担保責任を追及されれば、大きな金額を支払うことにもなりかねません。
そこで今回は、瑕疵担保責任の概要を解説し、実際のトラブル事例、および対処法も併せて解説していきます。
※2020年4月の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」という名前に変わりました。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
瑕疵担保責任を理解する
不動産売却時の瑕疵担保責任トラブルを回避するために最も重要なことは、瑕疵担保責任とは何か?をよく理解することです。
トラブル事例と対処法を解説する前に、まずは瑕疵担保責任の概要を解説していきます。
瑕疵担保責任とは?
引渡した物件に瑕疵(≒欠陥)があったとき、売主が補修などの対応をして、その瑕疵に対しての責任を取ること。
仮に、瑕疵の内容が重大である場合には、買主は売買契約の解除を求めることもできます。
瑕疵担保責任は売主にとっては大きなリスクで、何も知らないまま引渡しをするとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
瑕疵とは以下のようなことです。
- 一戸建ての土台部分にシロアリ被害がある
- 物件の壁部分に亀裂が入り雨が浸水してくる
- 天井から雨漏りがする
- 事故物件などの心理的瑕疵
瑕疵担保責任の期間
瑕疵担保責任の目的は、「隠れた瑕疵」による買主の損害を守るためにあります。隠れた瑕疵とは、売主も知り得なかった瑕疵のことです。民法上は、「買主が瑕疵を知った時から1年以内」が期限です。
例えば購入から10年後に買主が瑕疵を知ったとします。その場合、その1年以内は売主に瑕疵担保責任があるため、売主の立場からするといつまで経っても瑕疵担保責任があるということになります。
そのため、さすがに売主の責任が重すぎるということで、一般的な中古物件売買の場合には「引渡しから半年~1年」程度の期間を設けて、瑕疵担保責任が免責になる特約を付けます。
なお、売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法により瑕疵担保責任を負う期間を2年以上としなければなりません。
売主に悪意(瑕疵を知っていた)がある場合は話が別です。瑕疵について売主の悪意が認められた場合には、契約書に瑕疵担保責任の免責期限を設けていても損害賠償などを支払うことになります。
参考:RETIO判例検索
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/105-084.pdf
瑕疵担保責任のトラブルと対処法
瑕疵担保責任の概要が分かったところで、次は実際に起きたトラブル事例とその対処法について解説していきます。
住宅品質確保促進法による注意点
住宅品質確保促進法(品確法)とは、引渡し後も買主が安心して住めるように、新築住宅の瑕疵担保責任の期間を「10年間」に義務化した法律です。
新築住宅の分譲は基本的に建築・不動産業者が行うので、分譲業者が10年間の瑕疵担保責任を負います。
しかし、個人が売主の場合も品確法に該当すれば、10年間の瑕疵担保責任を負う場合があるので注意が必要です。
○宅建業者限定ではない
品確法で10年間の瑕疵担保責任を負うのは、宅建業者などの法人に限定されているわけではありません。
品確法は、売主が法人か個人かは問題ではなく、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)」とされています。
そのため、たとえば新築物件を購入して、何かの事情で未入居のまま転売しなければいけないときは、
個人の売主であっても瑕疵担保責任を10年負う場合があるということです。
○特約の効果はなくなる
仮に、売買契約書に「売主の瑕疵担保責任の期間は、物件引渡しから1年間に限る」という特約を付けたとします。しかし、この特約も付けても品確法の方が優先されるので、この特約は無効になります。
まずは、この点を理解しておきましょう。
○対処法
対処法ですがあらかじめ分譲主との間で、分譲主が品確法に基づく瑕疵担保責任を負う旨の書面を取得することです。
たとえば、A社が分譲した新築マンションを購入したBさんが、新築未入居のままCさんに売却するとします。
このままだと、品確法に基づきBさんが10年間の瑕疵担保責任を負う場合があるので、事前に分譲主であるA社との間で「A社がCさんに対して瑕疵担保責任を負う」旨の書面を交わしておくということです。
まずは、A社に相談しましょう。
新築・築浅物件の売却に関する詳しい記事はコチラから
引渡し前のトラブル
たとえば、一戸建ての売買契約を締結し、引渡し前に火事になり買主から契約解除を求められたとします。このケースも、広義の意味で「瑕疵担保責任」になります。
基本的に、売買契約では以下のような条文があります。
- 毀損に関しては売主が修繕をして引き渡し日が延びても買主は了承する
- 滅失した場合は売買契約は白紙解約になる
○売主の対応は?
前項のような条文内容なので、火事がボヤ程度の修復できるレベルであれば、売主が修復をして、買主も引渡しが延びる旨を了承するのが契約内容です。
しかし、心理的な瑕疵として、買主が「縁起が悪いから住みたくない」と思うかもしれません。
このようなケースで、仮に「契約解除になるか?引渡しか?」について訴訟になれば、判決はどっちに転ぶかは難しい問題でしょう。
○対処法
対処法としては以下が挙げられます。
- 保険は解約しない
- 引渡し日を早める
まず、火災保険や地震保険は引渡し日までに解約してはいけません。稀に、売買契約と同時に保険を解約してしまうケースがあります。
この場合、売買契約~引渡しまでは保険に守られていないということです。そのため、仮に火事になってしまえば、売主の負担で補修する必要があります。
また、引渡し日を早めることで、売買契約~引渡しまでの災害などに対してリスクヘッジすることができます。
この2点を頭に入れて取引しましょう。
ホームインスペクションの活用

前項で、瑕疵担保責任に関するトラブルと対処法を解説しました。
ほかの対処法として「ホームインスペクションの活用」があり、これは宅建業法改正によって注目されています。
ホームインスペクションとは?
ホームインスペクションとは、簡単に言うと「建物診断」のことです。
建築士や公認ホームインスペクターなど、有資格者や不動産業務従事者が、売却する物件を以下のように細かくチェックします。
- 基礎部分にひび割れはないか?
- 外壁部分に損傷はないか?
- バルコニーに破損などはないか?
- 壁や床に剥がれや腐食はないか?
- 天井にひびや水シミはないか?
このように、目視できる範囲は全て目視してチェックします。ただ、マンションの場合には基礎部分のチェックは難しいため、目視できる範囲に限定されます。
ホームインスペクションと瑕疵担保責任
ホームインスペクションを実施することで、瑕疵担保責任について以下のようなメリットがあります。
- 瑕疵を発見できる
- お墨付きをもらえる
まず、事前に瑕疵を発見できるという点が大きいです。瑕疵を事前に知っておくことで、買主に告知しておくことができますし、補修して引き渡すことでリスクヘッジできます。
また、仮に引渡し後「売主に悪意があったか?」などと問われた場合、ホームインスペクションを行っていることで売主に悪意はないという証明ができるのです。
ただ、ホームインスペクションには5~10万円程度かかるので、その点を加味して検討すると良いでしょう。
瑕疵担保責任は信頼できる不動産会社に相談しよう:まとめ
不動産を売却するときは、まず瑕疵担保責任の概要を理解しましょう。その上で、品確法に該当するときや、災害時の対処法について理解し、心配であればホームインスペクションの実施をおすすめします。
インスペクションを利用する場合は、事前に不動産仲介会社に相談することをおすすめします。
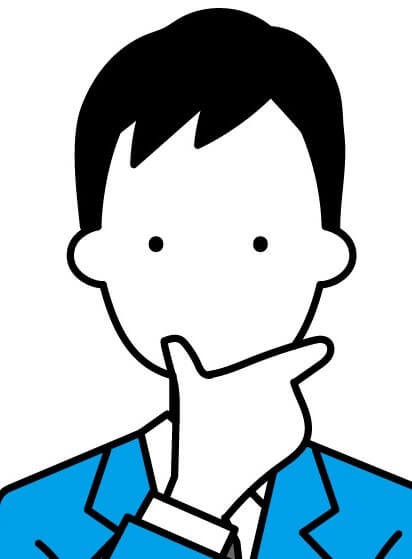
信頼できる不動産会社選びです!
不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。




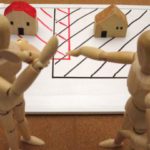



















このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)