「空き家法を守らなかったらどうなるの?」
「そもそも空き家法ってなに?」
こんな疑問にお答えします。
人口減少の一途をたどる日本では、全国各地に老朽化した空き家が増え続けています。
総務省の「2018年住宅・土地統計調査」によれば、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.6%で、5年前の13.5%を上回り過去最高水準になっています。
土地統計調査とは全国約350万住戸・世帯を対象に、5年に1度実施している基幹統計調査です。
引用:国土交通省「令和5年住宅・土地統計調査」
長きにわたって人が住んでおらず、そのことによって老朽化の進行が早くなり、火災や倒壊、さらには衛生上の問題や、不法侵入者による犯罪など、懸念される問題点が多くあります。
その対策のために、政府が定めた法律が「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き家法)です。
今回は、なぜ空き家のままにしておくのが問題なのか、そのデメリット、そして「空き家法」について詳しく解説します。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
目次
「空き家法」とはどのような法律なのか
空き家法は、平成27年5月26日より全面的に施行されました。
この法律では、放置されている空き家の所有者について、市町村に固定資産税の納税記録をもとに特定させ、立ち入り調査の権限を与えます。
特に老朽化が激しく、倒壊の恐れがあるなどの「特定空き家」については、解体撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることが規定されています。
つまり、市町村に対して
- 管理がなされずに放置されている空き家の持ち主を特定すること
- 対象の空き家に立ち入り調査を行う権限を与えること
- 危険度合が大きい空き家に関しては、持ち主に解体や修繕を命令し、従わない場合は持ち主に代わって市町村が解体撤去を行うこと
等ができると定めたものです。
市町村が解体撤去を行った場合、かかった費用は当然持ち主に請求されることになります。
空き家は個人の所有物ですが、老朽化が進んで周囲に悪影響を及ぼすことになれば、市町村がその空き家を処分できる権利を与えられるといえばわかりやすいでしょう。
空き家とはいえ、家も土地もれっきとした不動産であり、必ず所有者がいます。
「誰も住んではいないけれど、自分の家なのだから口を出さないでくれ」と思う所有者もいるかもしれません。
ましてや自分の意思に関係なく解体を命じられたり、それに応じなければ強制的に解体されてその費用を請求されるなど納得できないでしょう。
しかし、個人の持ち物であっても、それを放置することでその周囲に悪影響を及ぼすとなれば、何らかの対策を講じることが必要になります。
所有者が対策を講じないのであれば、市町村が代わって早急に対策をとることになります。
なぜ空き家を放置することが問題になるのか
空き家を放置するとさまざまな問題が起こります。家の老朽化が進み、悪臭を漂わせたり、空き巣や放火等の被害にあうことや、治安や衛生面では周囲の住民に悪影響を与えてしまいます。
特に木造住宅の場合は、空き家になると建物の老朽化の進行が早くなります。戸や窓を閉め切った状態が長く続くと、家の中に湿気がこもってしまいます。
人が住み、生活していれば、戸や窓の開け閉めが頻繁になされるため、空気が家の中を循環し、湿気がこもり続けることはありません。
空き家の状態になれば、そのこもった湿気によって木材の腐敗が進み、老朽化が早くなります。建物内の問題であれば、資産価値が無なくなるなど所有者自身の問題で済むことです。
しかし、さらに老朽化が進めば、その空き家の中だけではなく、建物外部の劣化が進み屋根瓦が落ちて周囲の危険を及ぼしたり、敷地内の雑草が伸びて周囲にも悪影響を及ぼすことになります。
空き家の倒壊・破損・散乱などの危険
 建物が老朽化することで、倒壊や破損、散乱などの危険性が高まります。
建物が老朽化することで、倒壊や破損、散乱などの危険性が高まります。
地震等によって建物が倒壊して道路をふさぐ、倒壊には至らないまでも外壁がはがれて道路に散乱する、台風の強風によって屋根などが破損して散乱する、などの可能性が考えられます。
特に、それらによって、近隣の家屋に損害を及ぼすことになったり、さらにはたまたま近くを通行していた歩行者に被害を及ぼすことになった場合、所有者が損害賠償責任を負わなければならなくなります。
これは民法第717条に建物の所有者の管理責任として定められており、その家屋に住んでいる、住んでいないにかかわらず課せられるものです。
また、「自然災害なのだから責任はない」との主張も通用しません。管理されずに放置されていたことが原因であったと判断されれば、損害賠償の責任が発生します。
そこに住んでいなくても、その空き家が他人や周囲に損害を与えないように管理する必要があるものと定められているためです。
さらに、空き家だけではなく、庭木や生垣が手入れされず荒れていることにより、周囲や通行者等に損害や被害を与えることとなった際にも、その空き家の所有者に責任が生じることになります。
放火等の危険
 放置された空き家は、放火に遭いやすいと言われています。もし放火された場合、ほとんどのケースでは所有者に法的責任が問われることはありません。
放置された空き家は、放火に遭いやすいと言われています。もし放火された場合、ほとんどのケースでは所有者に法的責任が問われることはありません。
しかし、管理不十分であることが原因で放火をされたという道義的責任を問う訴訟を起こされた場合、責任を追及される可能性もありますし、不動産価値の観点から考えると"瑕疵物件""いわく付き物件"ということになり、いざ不動産を売却する時に悪影響を与えることになります。
治安・衛生面での問題
 長らく放置され、所有者や管理者とみられる方の出入りがみられない空き家には、浮浪者や犯罪者、近隣の少年等が無断で侵入し、治安を悪化させる原因となることがあります。
長らく放置され、所有者や管理者とみられる方の出入りがみられない空き家には、浮浪者や犯罪者、近隣の少年等が無断で侵入し、治安を悪化させる原因となることがあります。
また、粗大ごみを中心とした不法投棄をされたり、それが原因となってゴキブリやハエなど害虫、ネズミ等の害獣の発生、棲みついた野良犬や野良猫の糞尿による悪臭の発生など、周辺地域に大きな問題を及ぼすこともあります。
それらが目立ち始めると、周辺の住人から役所に苦情が入り、確認と調査が行われたうえで所有者に是正の指導がなされることになります。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
空き家法によって、役所の強制代執行が可能になった
これらの危険性や問題等のトラブルは、原則として当事者同士で話し合いをするのが解決方法とされていました。
役所が介入できない案件とされていたわけです。
しかし、空き家法の制定によって、空き家の管理が不十分であるために起こったと考えられるトラブルについては、役所が介入して解決を図ることができるようになりました。
トラブルの仲裁をするのではなく、空き家の所有者に対して、必要と考えられる措置や対策をとるように指導できるのです。
その指示に従わず、必要とされる管理や対策を講じない場合は、役所が強制的に空き家の修繕や解体を行い、その費用を所有者に請求することができます。
空き家の放置を続けると「管理不全空き家」・「特定空き家」と判断される
空き家法は、すべての空き家を対象としているわけではありません。現在は空き家の状態となっていても、定期的な管理がされていれば問題はありません。
売却中であったり、賃貸入居者を募集中の空き家は管理されているはずですし、対象にはなりません。「空き家」と定義されるのは、年間を通じて管理がされていない空き家です。
その中でも、
- 窓や屋根・壁の一部が壊れていたり、雑草が生い茂ったりしている状態の空き家を「管理不全空き家」
- 倒壊等で保安上危険、衛生上有害となるおそれのある、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態等の空き家を「特定空き家」
と定義されます。
見た目でも安全上でも、誰の目からみても適切な管理のされていない、地域に迷惑になってしまっていた空き家が「特定空き家」に定義されるのです。
特定空き家と定義された場合のデメリット
固定資産税が3倍から4倍になる
特定空き家に対しては、税制上の優遇措置である「住宅用地特例」が受けられなくなります。
本来、家の敷地に対しては、固定資産税を算出する際に住宅用地特例が適用され、税額が最大で6分の1まで軽減されます。
しかし、人が住んでいないまま放置されている特定空き家には、その特例が適用されなくなるため、固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、税額が3倍から4倍になります。
どれだけ高くなるかは敷地の面積により変わります。
役所の行政代執行によって強制解体される
特定空き家として指定されれば、修繕や解体など必要な措置をとるよう、改善勧告をされます。
それに従わなければ、改善命令が出され、命令に従わず放置を続けると、代執行が行われます。役所により強制的に解体されるということです。
それにかかった費用は当然ながら特定空き家の所有者に請求されます。
空き家は放置せず売却するか活用すべき:まとめ
特定空き家と定義された場合、早急に何らかの手立てを行うべきです。その空き家の状態にもよりますが、修繕が可能であれば、売却するか、賃貸物件とすることが良いでしょう。
老朽化が激しく、修繕が困難であれば、解体して土地として売却するか駐車場等に使うなどを考えましょう。もしくは、「建物付土地」として現状のままで売却する方法もあります。
どの方法が最善なのかは、自分で判断せずに不動産会社に相談しましょう。
不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
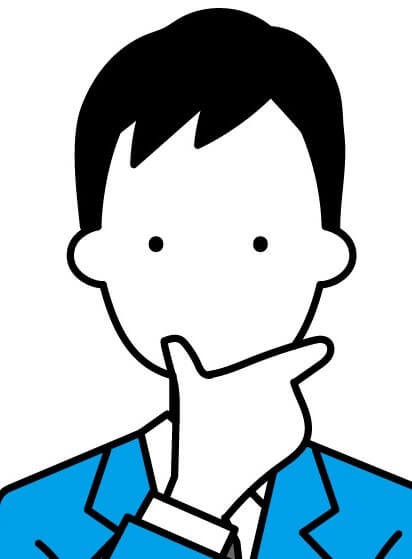
信頼できる不動産会社選びです!
























このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)