「不動産の相続登記ってどうやればいいの?」
「相続登記しなかったら罰則はある?」
こんな疑問にお答えします。
親が亡くなって実家の土地や建物の不動産を相続したら必ず「相続登記」をすべきです。
不動産の相続登記をしない場合、いろいろなトラブルや不利益の原因になってしまいます。今回は不動産を相続したときにまずやるべき「相続登記」について、詳しく解説します。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
目次
相続登記とは
相続登記とは不動産の相続が起こったときに所有名義人を書き換えること(不動産の名義変更)
不動産には「登記制度」があり、不動産の面積や種類、番号、所有者などの情報が公示されており、不動産の登記内容は誰でも閲覧できます。
ところが売買や相続などが起こると不動産の所有者が変わります。所有者が変わったのに登記名義人だけが前の持ち主(相続の場合には死亡した人)のままでは、誰が本当の所有者かわからなくて混乱が生じてしまいます。
そこで相続が起こったら、不動産の所有名義人を亡くなった人から相続人に書き換える必要があります。それが「相続登記」です。
3種類の相続登記
相続登記には以下の3種類があります。
- 遺言によって登記する
- 遺産分割協議で登記する
- 相続人が全員で法定相続分通りに登記する
順に解説します。
遺言によって登記する
遺言書が残されていて特定の人が相続する場合には、不動産の所有名義人はその特定の人の単独名義となります。
遺産分割協議によって登記する
相続開始後相続人たちが遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を相続することになった場合には、不動産を引き継ぐ相続人の単独名義となります。
参考:相続不動産の売却時に必要な遺産分割協議について5つのポイントで解説
相続人全員が相続する(法定相続)
遺言書もなく遺産分割協議も行わない場合に登記する方法です。
たとえば相続人が忙しくて遺産分割協議をする時間がない場合、遺産分割協議をしたくない場合やできない事情がある場合、遺産分割協議を行ったけれども意見がまとまらず決裂してしまった場合などには、遺言による登記も遺産分割協議による登記もできません。
しかし特定の相続人が決まらないからと言って、不動産の名義を死亡した被相続人名義で放置するのは不都合です。
そこで法定相続人全員の共有名義に登記をします。これを法定相続登記と言い、不動産は法定相続人それぞれが法定相続分に従った持分割合で「共有」状態になります。
共有名義にした後に遺産分割協議が成立した場合
当面遺産分割協議ができない場合、いったん法定相続人全員の共有名義にした後、遺産分割協議が成立した時点であらためて特定の相続人名義に登記することも可能です。
ただしその場合、共有名義にしたときと2回目に登記したときの2回分の手数料と手間がかかるデメリットがあります。
相続登記の流れ
相続登記を行うとき、どのような流れとなるのでしょうか?基本的に特定の相続人名義にする場合でも共有名義にする場合でも流れ自体は同じです。
以下では、司法書士に依頼せずに自分で相続登記を行うときの流れをご説明します。
相続登記の申請先は法務局
不動産の登記は「法務局」で管理しているので、相続登記は不動産を管轄する場所の法務局で行います。
登記申請書を作成する
相続登記をするときには「登記申請書」が必要です。法務局のホームページから該当する書式を選んで作成しましょう。
必要書類を集める
次に相続登記に必要な書類を集めます。必要書類はケースによって異なるので、別項目でご説明します。
法務局に提出する
登記申請書と必要書類が手元に揃ったら、まとめて法務局に提出します。その際登録免許税(相続登記の場合は不動産の固定資産評価額の0.4%)を支払います。
登記識別情報通知を受けとる
所有名義人が変更されて相続登記が完了すると新たな所有者には「登記識別情報通知」が交付されます。これは昔の「不動産権利証」と同じもので、不動産の真正な所有者であることを証明するためのものです。将来不動産を売却する際などにも必要になるので大切に保管しましょう。登記完了までに1~2週間程度かかります。
法定相続登記をする場合には、所有者は複数になりますが登記識別情報通知は1通しか交付されないので、金融機関の貸金庫など間違いのない方法で保管すべきです。
参考:不動産売却で必要な権利証ってなに?宅建士が4つのポイントで解説
相続登記の必要書類

相続登記をするときには、以下の書類が必要になります。
法定相続登記する場合
死亡した人の出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
⇒各謄本の本籍地の役所に申請をして取得します。郵送でも取り寄せ可能です。
死亡した人の住民票除票または戸籍の附票
⇒住民票は死亡した人の住民票のある市区町村役場、戸籍附票は現在の戸籍謄本の本籍地の役場で取得できます。
相続人の戸籍謄本
⇒それぞれの本籍地の役場に申請します。
相続人の住民票
⇒それぞれの住所地の役場に申請します。
相続関係説明図
⇒自分達で作成します。
固定資産評価証明書
⇒不動産が所在する場所の市区町村役場で申請します。
相続放棄した人がいる場合、相続放棄の受理書
⇒相続放棄したときに家庭裁判所から送られてきている書類です。なくしていたら再度家庭裁判所に「受理証明書」を申請します。
参考:相続不動産は放棄できる!?相続放棄について3つのポイントで解説
司法書士に依頼する場合には委任状
⇒相続登記を司法書士に依頼する場合には、相続人全員分の「委任状」が必要です。委任状は司法書士が用意するので、それぞれの相続人が実印を使って署名押印します。
遺言書によって登記する場合
遺言書
⇒自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、先に家庭裁判所で「検認」を受けておく必要があります。公正証書遺言なら公証役場で謄本を取得しておきます。
- 死亡した人の住民票除票または戸籍の附票
- 遺言によって不動産を取得する人の戸籍謄本
- 遺言によって不動産を取得する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 司法書士に委任する場合には委任状
委任状
⇒相続登記を司法書士に依頼する場合、申請者の委任状が必要です。この場合、遺言によって相続する相続人の分だけでかまいません(他の相続人による委任状は不要です)。
遺産分割協議によって登記する場合
遺産分割協議書
⇒遺産分割協議が成立したときに相続人全員が確認して作成する書類です。全員が署名の上、実印で押印しておく必要があります。
- 死亡した人の出生時から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
- 死亡した人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 相続関係説明図
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 相続放棄した人がいる場合、相続放棄の受理書
- 司法書士に依頼する場合、委任状
遺産分割協議によって不動産を相続する相続人による委任状が必要です。司法書士が書式を用意するので、実印を使って署名押印をして作成し、司法書士に渡します。
このように法定相続か遺言か遺産分割協議かで相続登記の必要書類が異なってきます。自分達がどのような方法で相続登記しようとしているのか理解して、ケースごとに正しい書類を集めましょう。
相続登記にかかる費用
相続登記をするときには、以下のような費用がかかります。
登録免許税
不動産の登記を行うときには「登録免許税」という税金がかかります。登記にかかる手数料のような費用です。
相続登記の登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
戸籍謄本などの取得費用
相続登記を行う際には、事前に大量の書類を集めなければなりません。郵送で役所から交付を受けないといけない資料が多いので、その際に手数料や費用が発生します。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本、改正原戸籍謄本は1通750円かかります。
住民票は1通200~400円程度、印鑑登録証明書も1通200~400円程度です(市区町村によって異なります)。
固定資産税評価証明書は1通300円程度です。
こういった書類を全部集めていくと、一般的に1万円~2万円程度は必要になります。
司法書士の費用
不動産の登記を自分で行うことも可能ですが、自分でやるとたくさんの書類を集めなければなりませんし、登記申請書を作成して法務局に持っていくなどいろいろと面倒です。
そこで登記を司法書士に依頼する方法があります。その場合、司法書士の報酬がかかってきます。
金額の相場は一般的に5~10万円程度です。相続登記だけではなく不動産に関する調査や遺産分割協議書の作成などを依頼すると費用が上がります。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
登記を自分でするか司法書士に依頼するか
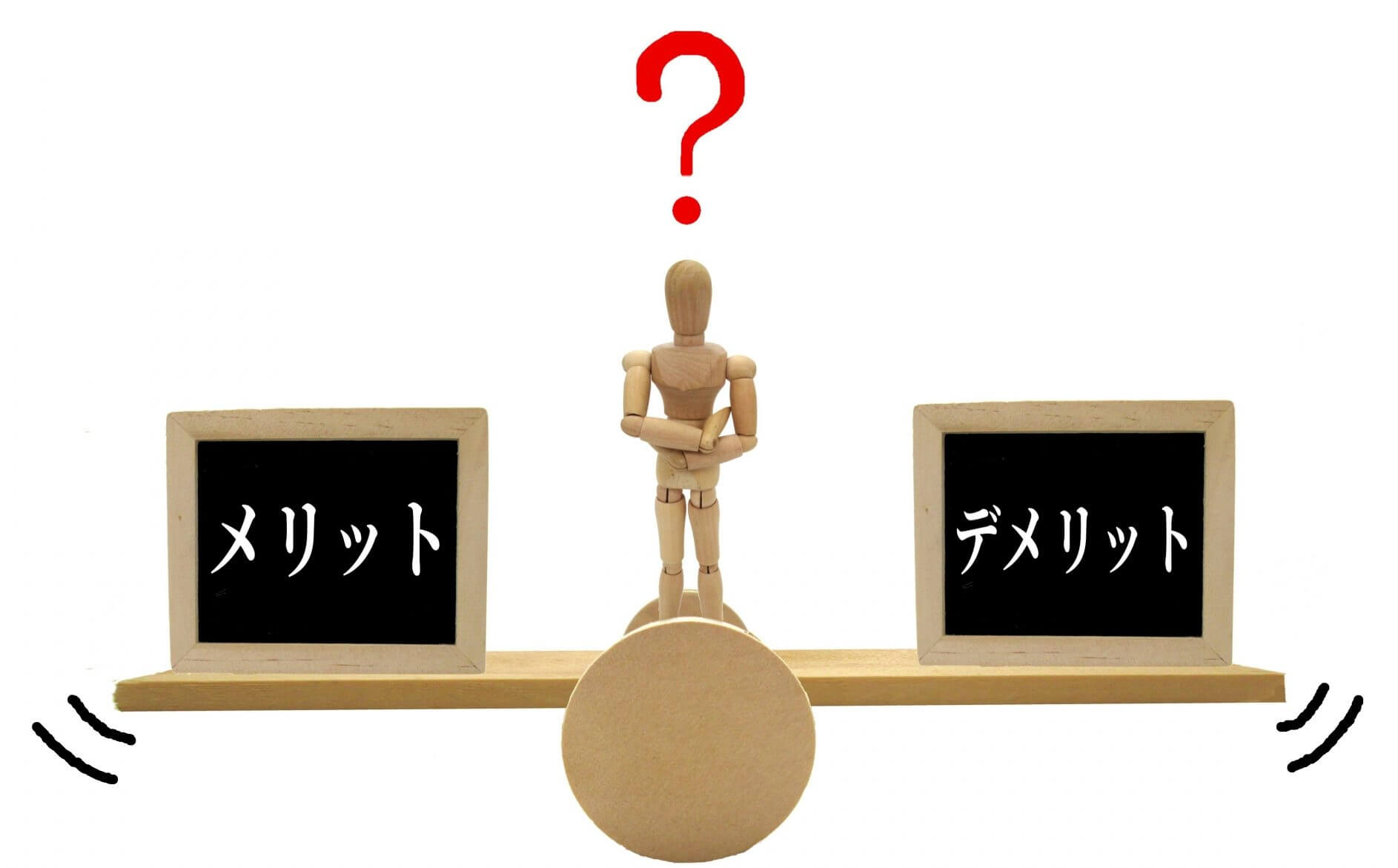
相続登記は、自分達で行うことも司法書士に依頼することも可能です。それぞれどういったメリットとデメリットがあるのか解説します。
自分達で行うメリットとデメリット
自分で行う場合には、費用を抑えられることが一番のメリットです。司法書士費用の数万円がかからないので、大幅に安くなります。
一方、非常に手間がかかる点がデメリットです。とくに戸籍謄本等の大量の書類を取得するのは大変な作業となります。
また登記申請書の書式をダウンロードして作成したり法務局に持っていったりするのも手間ですし、間違っていたらやり直しになるケースもあります。
司法書士に依頼するメリットとデメリット
司法書士に依頼すると、相続登記をスムーズにできるメリットが大きいです。委任状さえ渡せば後はほとんど司法書士が手続きをしてくれます。
戸籍謄本等の取り寄せも司法書士が職権でできるので、依頼者が自分で行う必要がありません。全部任せて待っているだけで登記完了の連絡とともに登記識別情報通知を渡してくれます。
デメリットは費用がかかることです。最低でも5万円程度は必要ですし、あれやこれやで10万円以上になってしまう例もあります。時間をとるか手間をとるかで依頼するかどうか決めると良いでしょう。
相続登記の完了が目的の場合は自分で行うのも良いですが、目的が売却の場合は司法書士に任せた方がリスクが少なくて良いです。
相続登記をしない場合のデメリット
相続登記は非常に面倒で費用もかかるので、不動産を相続しても名義を書き換えずに放置する人がいます。相続登記をしなかったらデメリットがあるのでしょうか?
他の相続人が勝手に不動産を処分する
遺言や遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を相続する場合、他の相続人は不動産について無権利です。
しかし相続登記をしないと誰がその不動産を相続したのかわかりません。とりあえず法定相続したようにも見えてしまいます。
すると本当は相続していない他の相続人が「法定相続割合で相続して共有状態になっています」などと嘘をついて、自分の法定相続割合に相当する部分を勝手に売却してしまう可能性があります。
不動産は、共有持分だけを処分することができるからです。
すると、嘘を信じて持分を買った第三者と真実の相続人との間で大きなトラブルが起こります。
無権利者が不動産を売却する
不動産の名義が死亡した人のままになっていると誰が本当の権利者かわからないので、すでに売却されて全く別の人になっている可能性もあります。
そこに目をつけて悪徳業者などが「この不動産は私のものです」などと言って事情を知らない第三者に売却することがあります。
基本的に無権利者による売却なので所有権は移転しませんが、騙されてお金を払った人と相続人との間で大きなトラブルが発生します。
将来相続が起こったときに混乱が生じる
今回相続登記をせずに放置していて問題が起こらなかったとしても、将来相続人が死亡すると再度相続登記の問題が発生します。(「数次相続」と言います。)
このとき、相続人の子どもたちにとっては「祖父の名義のまま放置されている不動産」となります。
すると、「実際には誰が不動産の所有者だったのか?」というところから調査しなければならず手間がかかります。
また相続登記は、いきなり祖父から孫へ名義を移すことができず、まずは祖父から父、その後父から子へ登記しなければならないので、集める書類もその分膨大となります。
このようなことが面倒なので再度不動産の相続登記を放置してしまい、いつしか持ち主不明の不動産になってしまうケースも多々あります。
将来の相続の際に子供達に迷惑をかけないためにも、今のうちにきちんと相続登記をしておきましょう。
相続登記は義務化される
今現在は義務化されていませんが、2024年4月1日より相続登記が義務化され罰則もあります。なるべく早めに登記をしてしまいましょう。
参考:相続登記が義務化されるって本当?宅建士が4つのポイントで解説
法改正について
現在は相続登記をしなくても相続人は第三者(無権利者から不動産を買った人など)に権利を主張できますが、2019年7月1日からは法改正により権利主張が難しくなりました。
相続登記をしないと、自分の法定相続分を超える部分については第三者に権利主張できなくなるのです。相続登記せずに無権利者に不動産を売却された場合に法定相続分を超える部分は失われてしまうリスクがあります。
こういった法改正に対応するためにも、不動産を相続したら早めに相続登記することが重要です。
不動産を相続したら早めに相続登記すべき:まとめ
相続登記は、相続したあなたの権利を守るための大切な手続きですから、たとえ期限や罰則がないとしても必ず行うべきです。
自分達でできない場合には、司法書士に依頼して早めに手続きをしましょう。
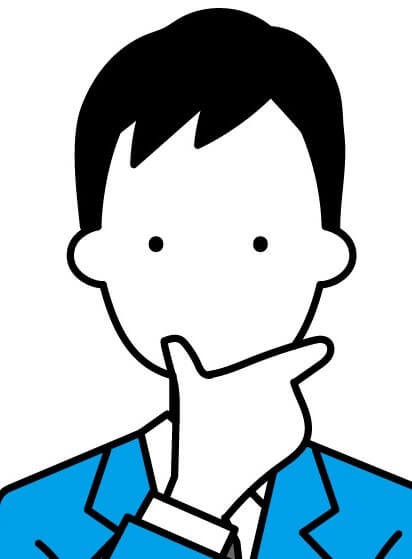
信頼できる不動産会社選びです!
不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。

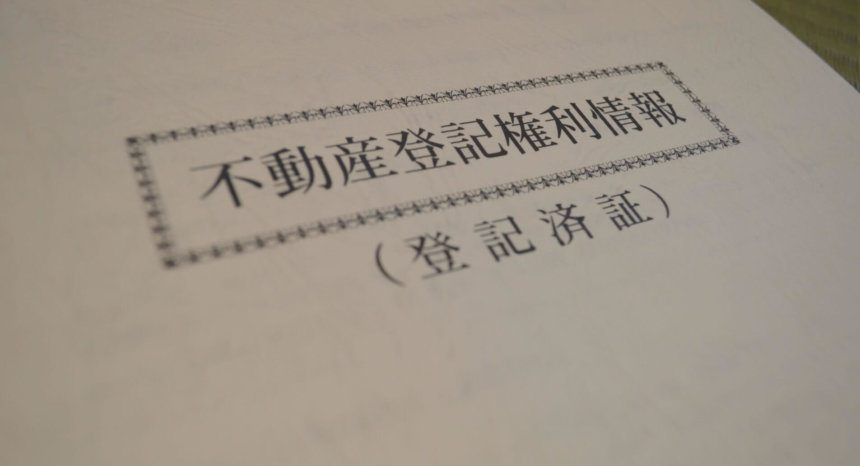






















このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)