「不動産を売却したら健康保険料が上がるの?」
「不動産を売却したら扶養からもはずれるの?」
こんな疑問にお答えします。
空き家を売却する場合や今の家を住み替えによって売却する場合、税金や諸経費について心配される方は多くいらっしゃいます。
しかし、不動産売却後の「健康保険料」にまで配慮される方は少ないのではないでしょうか?
実は不動産を売却して利益が出ると、翌年度の「健康保険料」が大きく上がる可能性があるので注意が必要です。
現在夫の健康保険の扶養に入っている方の場合、扶養から外れて自分で健康保険に入らないといけないケースもあります。
今回は、不動産売却によって健康保険料が上がったり扶養を外れたりするケースについて解説します。思わぬ損をしてしまわないようにしっかり学んでいきましょう。
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/
目次
健康保険の仕組み
いったいなぜ、不動産を売却したら健康保険料が上がってしまうのでしょうか?まずは健康保険の仕組みから簡単にご説明します。
健康保険は、保険に加入することによって医療機関を受診するときや薬を処方されたときの負担金額を1~3割に抑えられる制度です。残りの7~9割の部分は「保険」が払ってくれます。
医療費の一部負担(自己負担割合)について
〇現役世代よりも軽い1割負担の窓口負担で医療を受けられます。
それぞれの年齢層における一部負担(自己負担)割合は、以下のとおりです。
・75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割)
・70歳から74歳までの者は、2割※(現役並み所得者は3割)
・70歳未満の者は、3割。6歳(義務教育就学前)未満の者は2割
※平成26年4月以降70歳となるものが対象。これまで予算措置により1割に凍結してきたが、世代間の公平を図る観点から止めるべき等との指摘を踏まえ、平成26年度から、高齢者の生活に過大な影響が生じることがないよう配慮を行ったうえで、段階的に2割とした。
このように、実際に負担する医療費を抑えることによって「お金がないので病院に行けない」人をなくし、国民が全員医療を受けられるようにしています。
日本では、すべての国民は何かの健康保険に入らねばならないという「国民皆保険制度」となっているので、誰でもどこかの健康保険に入っています。
そして健康保険に入っている人は、基本的に「健康保険料」を払わなければなりません。その金額は収入や都道府県よって異なります。
この健康保険料が、不動産売却によって上がってしまう可能性があるのです。
健康保険の種類と健康保険料の決まり方
健康保険にはいくつかの「種類」があり、それぞれ不動産売却によって受ける影響の内容が異なります。以下では健康保険の種類と、それぞれの保険料の決まり方をご説明していきます。
健康保険への加入形態は、大きく分けて以下の5種類に分けられます。
- 社会保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 共済保険
- 被扶養者
順に解説していきます。
社会保険
社会保険は、企業で働くサラリーマンが加入する保険です。通常、民間企業に勤務する場合には、会社で「社会保険」に入っています。
一般的に「社会保険」と呼ばれるものの中に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」があります。
会社の社会保険を引き受けているのは「健康保険組合」か「協会けんぽ」です。比較的大きな企業の場合には独自の健康保険組合を作っていたり、どこかの健康保険組合に加入していたりすることが多いですが、小さい企業だと協会けんぽに入っているケースが一般的です。
健康保険組合には、地域や業種によってさまざまなものがあります。自分が加入している健康保険組合を知りたい場合、一度会社に確認すると良いでしょう。
会社員の場合、社会保険の健康保険料は毎月の「給料」から天引きされています。健康保険料などの社会保険料の金額は、本人の「給与額(標準報酬月額)」に応じて計算され、給与額が上がれば健康保険料も上がる仕組みになっています。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業者などの「お勤めをしていない人」が加入する健康保険です。フリーランスや不動産収入で生活している方も国民健康保険に加入しています。年金生活者や無職の人も75歳未満であれば国民健康保険に入ります。
国民健康保険を運営しているのは「市区町村」です。そこで、健康保険料は市区町村に対して払う必要があります。
毎年市区町村から健康保険料の納付書が送られてくるので、それを使って金融機関等で支払いをするか、銀行口座からの引き落としにします。
国民健康保険料の金額は、各自治体によって大きく異なります。ただどこの自治体でも「前年度の所得」に応じてかかってきます。前年度大きくもうけが出ると、翌年度の健康保険料が高額になります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の「後期高齢者」に適用される健康保険制度です。
後期高齢者については、一般の国民健康保険とは別に独立した保険制度が作られています。
後期高齢者医療制度を運用しているのも、国民健康保険と同様市区町村です。この場合にも、前年度の本人の所得に応じて金額が変わります。
一般的に後期高齢者は年金生活者が多いので、年によって保険料が大きく変動することは少ないのですが、何らかの理由で所得が増えると健康保険料が増額される可能性があります。
共済保険
共済保険は、公務員や準公務員が加入する健康保険制度です。公務員については、健康保険や年金が「公務員共済組合」という特別の団体によって運営されています。
そこで共済組合に健康保険料を払い、共済組合から医療費の補助を受けることとなります。
公務員の場合、共済の健康保険料の金額は会社員と同様に毎月の給与額(標準報酬月額)によって決まります。給料の高い人はその分健康保険料も上がる仕組みです。
被扶養者の場合
以上の健康保険はすべて「自分自身が保険に加入している」人の話でしたが、実はこれら以外に「被扶養者」と呼ばれる人がいます。
被扶養者とは、家族の扶養に入っているので自分では独立して健康保険に入っていない人です。典型的な被扶養者は「会社員の妻、子ども」や「公務員の妻、子ども」です。
つまり収入が一定以下の家族の場合には、自分で健康保険に入らず、扶養者の健康保険に入れてもらうことができるのです。
被扶養者になるための収入の限度額は以下の通りです。
- 一般の被扶養者の場合…年間収入が130万円未満
- 60歳以上や障害者の場合…年間収入が180万円未満
被扶養者の場合には、自分自身で健康保険料を払う必要がありません。夫が給料から健康保険料を天引きされていたら、配偶者は無料で健康保険を使って病院を受診できます。
ただし「扶養」の概念があるのは、「社会保険」と「共済保険」のみです。「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」には「扶養」という制度がありません。
そこで、夫が自営業者の場合などには妻は夫の扶養に入ることはできず、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
不動産売却によって健康保険料が上がる可能性

不動産を売却すると、上記の健康保険料に対してどのような影響が及ぶのでしょうか?健康保険の種類ごとに確認しましょう。
社会保険の場合
サラリーマンなど社会保険に加入している方の場合、不動産を売却しても健康保険料に「影響はありません」。
社会保険の場合、健康保険料の算定根拠はすべて「標準報酬月額」という給与額にもとづいた指標だからです。
売却益が出ると所得税や住民税が余計にかかる可能性はありますが、健康保険料については別計算となるので影響がありません。
よって、会社員が不動産を売却して大きな利益を出しても、翌年にいきなり健康保険料が大きく天引きされる心配はありません。
もしも健康保険料が上がったら、別の原因と考えられるので、一度会社や健康保険組合に問い合わせると良いでしょう。
ただし健康保険料は増額されなくても、所得が上がることによって住民税が上がります。
国民健康保険の場合
自治体の国民健康保険に加入している方の場合、不動産売却によって利益が出ると大きな影響が及びます。
国民健康保険料は、前年度の「所得」に応じて計算されるからです。不動産売却の所得は「分離課税」となっています。
事業所得や給与所得などの他の所得とは別に独立して税額を計算される制度です。確定申告などの際にも不動産については事業所得と別に申告します。
ただ、分離課税であっても国民健康保険料の算定根拠になります。そこで不動産を売却して譲渡所得が発生した方は、翌年の健康保険料が大幅に上がる可能性があるのです。
増額される具体的な金額は自治体によって異なりますが、年間70万円以上の健康保険料がかかる地域もあります。
後期高齢者医療制度の場合
75歳以上の後期高齢者医療の場合にはどのような影響が及ぶのでしょうか?
後期高齢者医療制度も、国民健康保険と同様に自治体が運営していて「本人の前年度の所得」に応じて計算されます。
そこで不動産売却によって大きな利益が発生したら、その分健康保険料が上がってしまいます。
後期高齢者の健康保険料は通常年金からの天引きとなります。年金からは、所得税や住民税、介護保険料なども天引きされますが、前年度の所得が高くなると所得税や住民税も高額になります。
つまり不動産売却によって健康保険料や税額が増額されると、翌年度の年金の手取りが減ってしまい、生活がかなり苦しくなるおそれもあり要注意です。
共済保険の場合
公務員共済の場合、不動産売却によってどのような影響が及ぶのでしょうか?
公務員の場合、会社員と同様にほとんど影響はありません。公務員の共済保険の保険料は、会社員と同様「標準報酬月額」によって独立して計算されているからです。不動産売却などによる別の儲けがあってもそれが健康保険料に加算されることはありません。
ただし会社員のケースと同様、所得が増額されることによって住民税の天引き額が上がります。
被扶養者の場合
奥さんやお子様など、会社員や公務員の「被保険者」となっている方の場合、不動産を売却するとどうなるのでしょうか?
この場合、以下の2つの問題があります。
① 被扶養者から外れる
1つは、夫などの「被扶養者」から外れてしまうことです。現在、健康保険の被扶養者になるためには、収入が130万円未満でなければなりません。
60歳以上や障害者の場合には180万円未満が基準です。
参考:被扶養者の認定要件(日本年金機構サイト)
不動産を売却してそれ以上の所得を得てしまったら、夫の被扶養者でいることはできないので、自分で自治体の国民健康保険に入らねばなりません。
その場合、昨年度の不動産売却益に応じた高額な健康保険料がかかってしまいます。
なお、不動産を売却した翌年に特段の所得がなかったら、その次の年度にはまた夫の被扶養者に戻ることが可能です。
②夫の税金が上がる
もう1つの問題は、夫の税金が上がってしまうことです。
妻が夫の扶養に入っている場合、夫は「配偶者控除」によって所得税の減額措置を受けています。
ところが妻が不動産所得を得て扶養から抜けてしまうと、配偶者控除が適用されなくなって税額が上がってしまいます。
夫自身の健康保険料は上がらなくても住民税や所得税が上がることにより、手取り額が減ってしまう可能性があります。
なお、健康保険の被扶養者となる要件は「年間収入が130万円未満」ですが、所得税の配偶者控除の要件は「年間所得が48万円以下」です。要件が異なるので押さえておきましょう。
健康保険料が上がるケースと上がらないケース

国民健康保険や後期高齢者の方、被扶養者の方であっても、不動産を売却したからといって必ずしも健康保険料が上がるとは限りません。
以下で上がるケースと上がらないケースの区別について解説します。
譲渡所得税が0以下になったら健康保険は上がらない
不動産売却によって健康保険料が上がるのは、売却によって「利益」が発生したからです。利益の分が所得に上乗せされるので、その分健康保険料が上がる仕組みです。
そこで不動産を売却しても「利益」がでなかったら健康保険料は上がりません。
つまり、不動産を購入したときよりも売れた代金の方が安い場合や、仲介手数料などの経費も入れると損になってしまった場合には、譲渡所得はマイナスです。
この場合には、国民健康保険料などが上がる可能性はありませんし、被扶養者を抜けてしまう心配もありません。
むしろ、損益通算することによって所得を減らし税額を減額することも可能となります。
損益通算とは、不動産所得と事業所得や給与所得などの別の所得をすべて差引計算して税額を計算する方法です。事業所得がプラスでも不動産所得がマイナスなら、その分所得から差し引いて税額を減らしてもらえます。
居住用不動産の3,000万円控除の特例について
仮に上記の計算式による譲渡所得がプラスであっても、譲渡所得税や住民税を0にして健康保険料の増額を抑えられる可能性があります。
それは「居住用不動産の3,000万円控除の特例」を適用できる場合です。
居住用不動産の3,000万円控除の特例とは、家や居住用マンションなどを売却して得られた譲渡所得については3,000万円分まで0円カウントにしてもらえる制度です。
つまり家を売って得られた利益が3,000万円までの場合、所得が0円なので譲渡所得税も住民税もかかりません。当然健康保険料に対する影響もありません。翌年から健康保険料が上がる心配も要りませんし被扶養者のままでいられます。
参考:5分でわかる!3,000万円特別控除とは?【マイホーム売却編】
要は、「居住用3,000万円特別控除」と「住宅ローン特別控除」の併用ができないということです。
不動産を売却するなら不動産売買のプロにご相談ください:まとめ
不動産売却によってせっかく利益が出ても、翌年に大きく健康保険料が上がってしまったり、配偶者が扶養から抜けてしまったりすると、損をした気分になることでしょう。
不動産を売るときには、こうした付随的なことについても正しく理解して進める必要があります。
不動産売却についてのさまざまな疑問は、一人で悩まず不動産売買のプロに任せることが大事です。
不動産会社選びで、家は数百万円「売値」が変わります。
査定価格は不動産会社によって違うので、高く・早く売るなら、複数の不動産会社の査定価格を比較することが大切です。
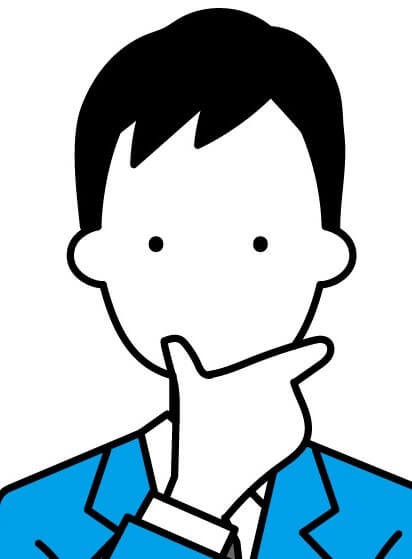
信頼できる不動産会社選びです!
\厳選2,300社と提携・国内最大級!/

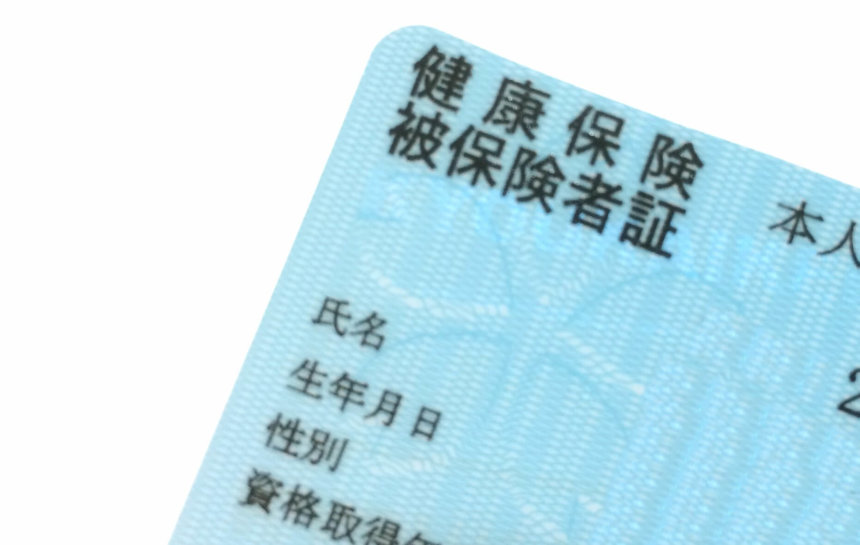

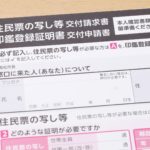




















このサイトから多数の査定依頼を受けています。(NHK・経済誌の取材実績も)